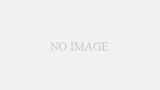サッカーの中で「最後の砦」と呼ばれる存在、それがゴールキーパー(GK)です。
味方の守備が崩れ、相手がフリーでシュートを打ってきた――そんなピンチの場面でも、体を張ってゴールを守り抜くキーパーの姿には、思わず胸が熱くなる瞬間がたくさんあります。
ときには体を投げ出し、ときには指一本でシュートを止める――そんなプレーは、まさにヒーローのようなかっこよさ!
ところが現場では、「キーパーやってくれる人いない〜!?」と声をかけても、子どもたちはなぜか目をそらしてしまう…そんな“あるある”も。
実はゴールキーパーは、かっこいいけれど、とてもハードなポジション。
しかも、サッカーを始めたばかりの子どもたちは、どうしても「点を取るストライカー」や「ゲームを支配する司令塔」といった目立つポジションに憧れを持ちがちです。
そのため、ゴールキーパーには“地味”というイメージを持ってしまうことも少なくありません。
ですが、そんなゴールキーパーには、他のポジションにはない特別な魅力とルールがあるのをご存じでしょうか?
この記事では、そんなゴールキーパーの役割と、最低限知っておきたい基本ルールを、
これからサッカーをもっと知りたい保護者の方に向けて、やさしく・楽しく解説していきます!
ゴールキーパーの役割とは?

1. ゴールを守る
キーパーの最大の役割は、なんといってもゴールを守ること。
サッカーで唯一、手を使うことが許されている特別なポジションで、体全体を使って相手のシュートをブロックします。
ボールを止める瞬間の迫力や緊張感は、見ている側もドキドキ…。
まさに“最後の砦”として、ゴール前に立ちはだかる重要な存在です。
2. 味方への指示出し(コーチング)
キーパーはコート全体を後ろから見渡せるため、フィールドプレーヤーに対して声をかけてサポートすることも大切な役割の一つです。
「後ろから相手が来てるよ!」
「ラインを上げて!」
「あそこにスペースがあるよ!」
といった声かけを通して、守備のバランスを整えたり、味方のポジショニングを修正したりする場面も多く見られます。
3. 攻撃の起点になる
守備のポジションというイメージが強いキーパーですが、実は最近では攻撃のスタート地点にもなっています。
ゴールキーパーからパスをつなぎ、ビルドアップ(攻撃の組み立て)を行うチームが増えてきたことで、キーパーには足元の技術も求められるようになってきました。
ただシュートを止めるだけでなく、味方に正確にパスを出せるキーパーは、チームにとってとても頼もしい存在です。
ゴールキーパーに関する基本ルール
ここからは、ゴールキーパーに関わる基本的なルールを3つご紹介します。

1. バックパスを手で取ってはいけない(バックパス禁止)
味方が足で蹴ったボールを、キーパーが手で触ると反則になります。
この場合、相手に間接フリーキックが与えられます。
ただし以下のケースでは、手で取ってもOKです:
- 味方が頭・胸・太ももでパスしたとき
- 味方のキックが意図的なパスではなく、クリアミスや足でのブロックだったとき
2. 6秒ルール
ゴールキーパーがボールを手でキャッチした後は、6秒以内にボールをリリース(投げる・蹴る)しなければいけません。
これは、時間稼ぎを防ぐためのルールで、もし6秒以上持ち続けると、間接フリーキックの対象となります。
とくに試合の終盤やリードしている場面では、審判もこのルールに厳しくなることがあります。
ただし、この「6秒ルール」ですが、 2025~2026シーズンのルール改正によって6秒→8秒に時間が延長され、間接フリーキックではなく、コーナーキックが与えられる様に変更されます。
3. 自分で蹴ったボールをすぐにもう一度触るのは禁止
ゴールキックやフリーキックなどでキーパーがボールを蹴った後、ほかの選手が触る前にもう一度自分でボールを触るのはNGです。
この場合も、間接フリーキックが相手ボールで再開されます。
一度味方や相手が触れれば、その後に触ってもOKです。
まとめ|ゴールキーパーは“特別なヒーロー”
ゴールキーパーは、サッカーの中でもひときわ特別な役割を担うポジションです。
ゴールを守ることはもちろん、味方への指示や攻撃の起点にもなるなど、試合のあらゆる場面に関わります。
そして、そのプレーには他の選手とは異なるルールがあるため、保護者の皆さんもそれを知っておくことで、
お子さんがキーパーを任されたときに、しっかり応援してあげられるようになります。
「なんで手を使っちゃダメなの?」
「今のって反則なの?」
そんな疑問も、ルールを知っていれば、親子で一緒に楽しく学ぶことができます!
ぜひこの記事をきっかけに、
「ゴールキーパーってかっこいい!」という視点を、親子で共有してみてくださいね✨
✅ この記事を読んだ方にはこちらもオススメ!